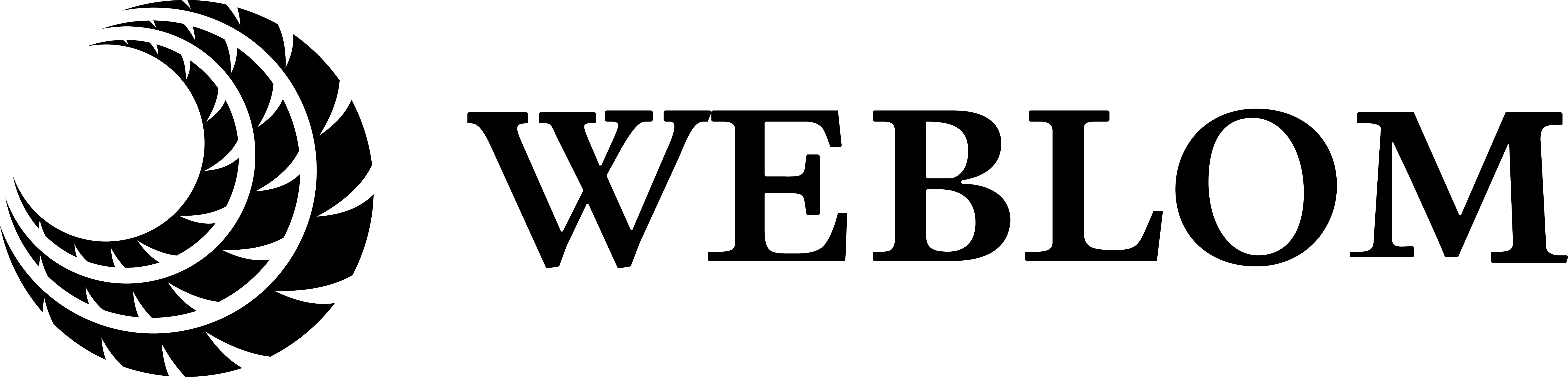今回は、現役WEBディレクターの私が、普段どんな提案、プレゼンをしているかお伝えしていこうと思います。
筆者は、過去には省庁案件や5,000万円規模のECサイトも受注しています。
WEBディレクターの提案、プレゼンとは
一言でいうと、クライアントの要望に対して、「私たちにシステム開発・導入を任せてもらえれば、御社の要望を叶えられます。」と伝えることです。
クライアントの抱える課題や悩みを汲み取り、どんなコンテンツを掲載して、どんなシステムを構築して、どんなサービスと連携をして、サーバーの構成はこうしますといった具合に、プレゼン提案をしていきます。
WEB制作の現場では、コンペ形式が多く、競合社数は2~5社が一般的です。
提案前の見積の段階で2社まで絞るといった企業も多いです。
ポイント1:プレゼンは慣れたツールで行う
プレゼンは、自分が使いやすい、慣れたツールで実施してください。当たり前かと思いますが、慣れはかなり重要な要素です。
スライドのめくり方やポインターの利用などでもたつくと、テンポが悪くなってグダグダになりがちです。プレゼンの中身がよくてもそれだけで落選することも全然あります。
私は、GoogleスライドかPowerPointで作った提案書をクライアントに説明しながら進めています。それにプラスして、XDでワイヤーフレームを作成していました。
クライアントにスムーズに内容が伝わればいいので、会社で決まり等がなければ、好きなツールを使ってください。重要なのは、慣れているかどうかです。
プレゼンで使うツールが決まったら、ツールの利用方法をマスターすることに注力しましょう。
必ず、財産になります。
ポイント2:プレゼンで考えること
プレゼンを受ける立場になって考えることが重要です。これも当たり前ですが、プレゼンの準備に精一杯になってしまうと、自分本位のプレゼンになってしまい、聞き手を置いてけぼりにしてしまいます。
プレゼンの前に、誰が決済者なのか、誰が稟議を申請するのかを把握するのが重要です。
聞き手によってプレゼンは変えます。
決裁者向けのプレゼンなら、予算とマネタイズは外せません。コストと利益はかなり深く見られます。業務効率化できますだけでは通用しません。業務効率化したうえで、これだけのメリットを与えられるといったところまで詰めます。
稟議者向けのプレゼンなら、上司にどうやって伝えるかを一緒に考えるようなプレゼンが刺さります。あなたのプレゼン資料をそのまま稟議にだせる資料にしてあげると、かなり高い評価を得られます。
プレゼンの流れ
プレゼンの流れを大きく分けると、
- 会社紹介
- リニューアルであれば、課題、改善案
- 新規構築であれば、作る目的 何を目指すか
- デザイン案をつくっていればデザインの説明(デザイナーにコンセプトを聞いておく)
- 運用デモンストレーション
- 制作スケジュール
- 制作体制
- 実績
順番はずれたりしますが、説明項目としては上記の通りです。
1回のプレゼンには1時間程度かかります。案件によっては2時間かかることもあれば、15分しかないこともあります。時間に合わせて配分は事前に整理しておきましょう。
それでは1つずつ説明していきます。
会社紹介
文字通り、自社の所在地、従業員規模、業種構成、沿革、特徴などを説明します。事前の打ち合わせで説明していたら省略します。
課題、改善案 リニューアルの場合
いま運用しているWEBサイトのリニューアル案件の場合は、事前にヒアリングした課題を洗い出して、改善案を提案します。
例えば、お客様からのお問い合わせを増やしたいといった場合は、UI(ユーザーインターフェース)に問題があるので、よりお客様がお問い合わせをしたくなるようなデザインに変更しましょうといった具合でお話しします。ワイヤーフレームまで用意できるとGood。
お金の話もここでします。
課題、改善案 新規構築の場合
新規構築であれば、なにを目的として構築するのかを提案します。
新しく作るWEBアプリやシステムを作ることで、なにを実現できるのか提案します。
例:
いまは顧客管理をExcelでやってるが、より簡単で誰でも管理できるようなシステムに入れ替えたい。
上の例のような相談がクライアントからあり、新システムの導入を提案する場合で説明します。
この内容で相談を受けた際に、
「私たちは我々にしかできない経験や技術力で、新しい顧客管理システムを構築します。」
といったような提案だけでは足りません。
上記は、システムを導入した際の付加価値に対する提案がないため、決定打に欠けます。
システムは作れて当たり前、システムを作ったうえでどのような付加価値があるかまでを提案に盛り込みましょう。
例えば、新しい顧客管理システムを弊社で導入すれば、御社独自の機能を柔軟に盛り込み、実際の運用に寄り添った仕様を実現させていただくので、運用を簡素化し、人的コストをダウンさせられます。
という提案であれば、「運用コストダウン」という付加価値をアピールできます。
クライアントは、「どんなシステムを作るか」は興味がないです。「どんな価値を提供してくれるか」に興味があります。
お金の話もここでします。
サーバ構成
少し専門的ですが、サーバ構成まで踏み入った提案を要求される場合があります。その場合は事前に開発チームに相談し、サーバーの構成図を作成するようにしましょう。
サーバーに関する基礎知識をもったうえで相談しないと時間を無駄にしてしまうので、事前準備は忘れずに。よければ、以下記事を参考にしてください。
デザインの提案
提案によっては、デザインが必須の場合もあるので、その場合はあらかじめデザイナーにお願いしておきます。それを提案書にはめ込んで説明します。
その際、デザイナーにデザインするうえで意識したことを確認し、クライアントに対してデザインポリシーを説明できるようにしとくと、提案に説得力が増します。
デザインポリシーを説明できないと、デザインの根拠が説明できないので、かなりマイナスです。
デザインではなく、私のようなWEBディレクターがつくったXD(デザインツール)で説明することも多いです。
運用デモンストレーション
実際のPC画面を共有しながら使い方を説明します。
デモサイトを使って、クライアントの運用イメージを画面で見せてあげることが重要です。
制作スケジュール
自社内で調整したスケジュールを提案します。
制作体制
WEBディレクターは1人、デザイナーは1人、開発は2人みたいにそれぞれのポジションにつく人数と相関図を伝えます。
クライアントによっては、各ポジションメンバーの経歴を聞かれたりします。
実績
いままでの会社、個人での制作実績を紹介します。プレゼンする会社に併せて、紹介する実績は変えてください。
あとは質疑応答で、クライアントからの質問に答えてプレゼン終了です。
プレゼンが終われば、一段落ですね。あとは、クライアントからの合否の連絡を待つだけです。
補足:コンペに勝ったら
無事提案が完了し、コンペを勝ち抜いたらプロジェクト始動です。
しっかり準備をすすめるために、まずはアクションアイテムを作成しましょう。
WEBLOMでは、以下記事にてアクションアイテムのテンプレートを無償で提供しています。
ぜひご活用ください。
おわり
今回は、WEBディレクターが行うプレゼンについて、ご説明していきました。プレゼンの技術もクライアントからの信用度に大きく関わってくるので、自分なりのやり方を確立して、常にリラックスして望めるといいですね。
以上、また次の記事でお会いしましょう。