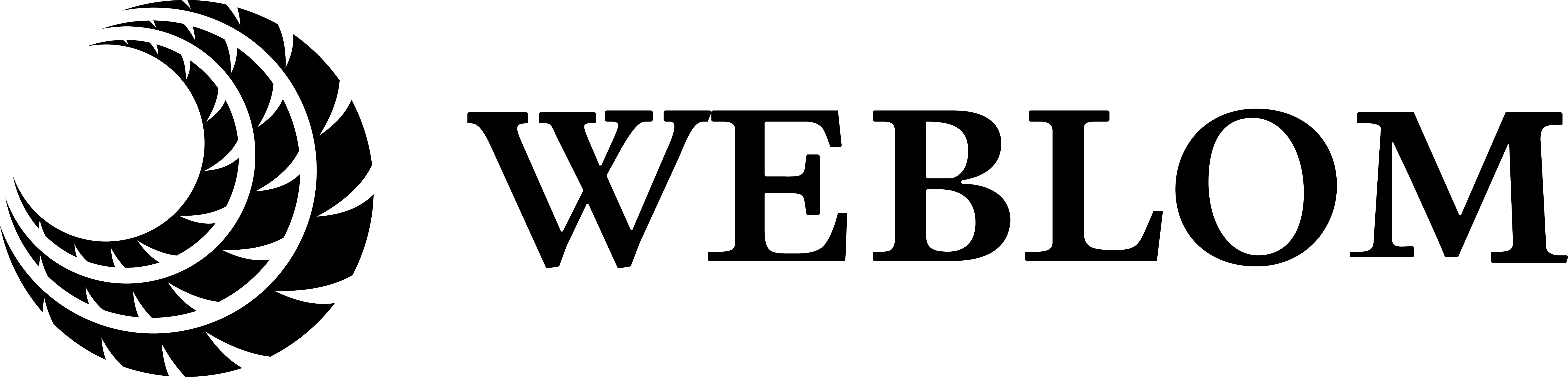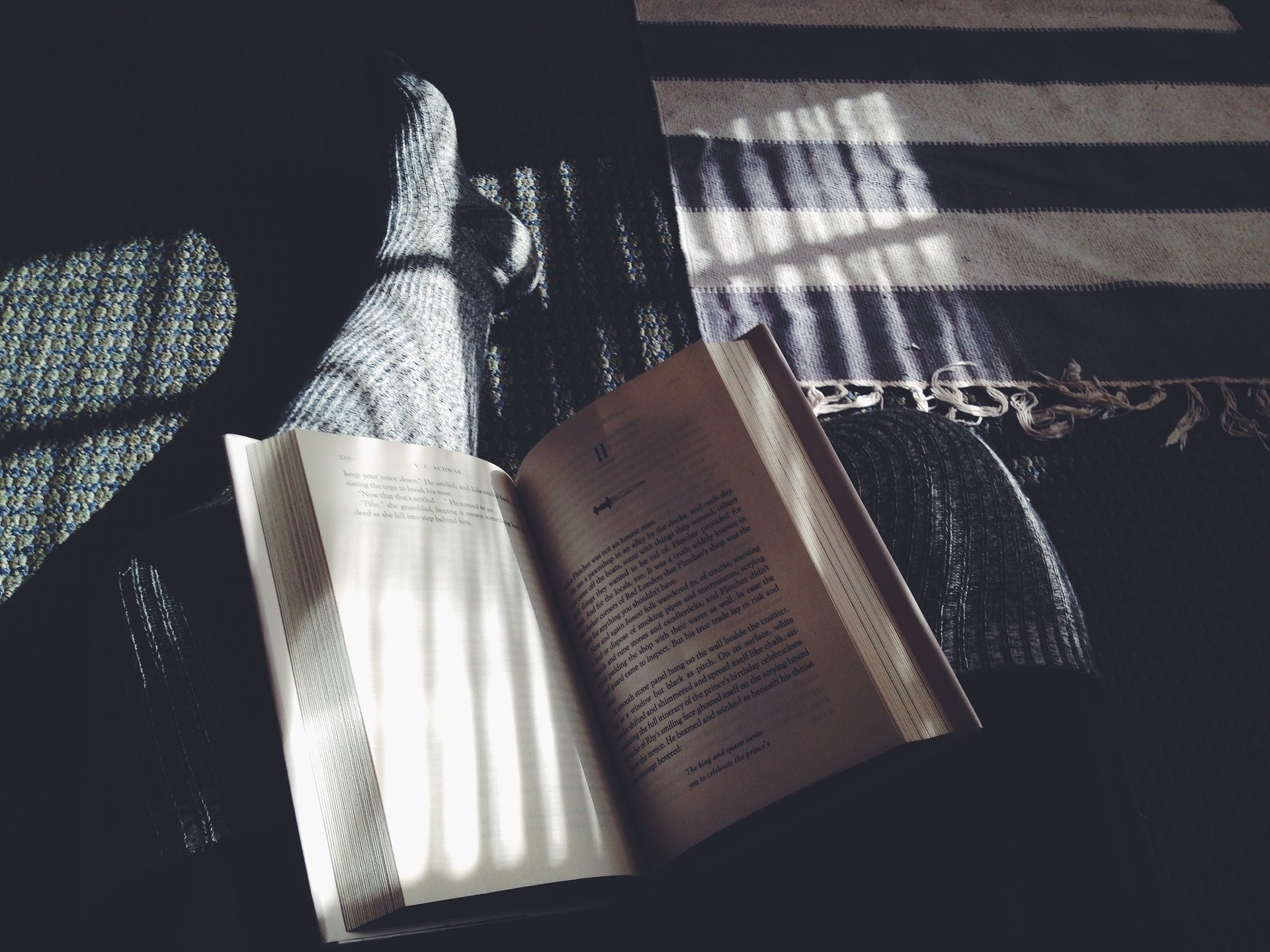近年、AI技術を活用して画像を立体的なフィギュアに加工する事例が増えてきました。
アニメキャラクターや写真をAIに読み込ませて立体化する――そんな未来的な試みは魅力的ですが、法的なリスクも少なくありません。
本記事では、作成者(フィギュアを作る側) と 購入者(フィギュアを買う側) の両面から、注意すべき法的ポイントを整理します。
作成者(AIでフィギュアを作る側)の法的リスク
著作権法上の問題
- 翻案権(著作権法第27条)
イラストや写真を立体化する行為は「翻案」にあたり、原著作物の権利者の許可が必要です。無断でAI加工してフィギュア化すると、著作権侵害にあたる可能性が非常に高いです。 - 複製権(第21条)
AI処理の過程で元画像を複製・保存する行為も権利侵害の対象になります。 - 頒布権・公衆送信権
加工したフィギュアを販売・展示・公開する場合、追加で権利侵害リスクが発生します。
契約・利用規約違反
AIサービスや素材には「非商用利用のみ」「二次利用禁止」といった規約が設定されています。これを無視して販売・公開すれば契約違反となります。
肖像権・パブリシティ権
元画像が実在人物なら、無断で立体化すると肖像権やパブリシティ権を侵害するリスクがあります。特に芸能人やモデルなど商業的価値のある人物は注意が必要です。
👉 結論(作成者側)
AIで著作物を立体化するには、原著作者や人物本人から必ず許可を得る必要があります。
無断利用は違法リスクが極めて高い行為です。
購入者(AIフィギュアを買う側)の法的リスク
著作権侵害の関与
購入して自宅で楽しむだけなら、原則的に著作権侵害の主体にはなりません。しかし、SNSに投稿したり、展示・販売した場合は「公衆送信」や「頒布」にあたり、侵害に加担したと見なされる可能性があります。
非公式品・違法品の購入
正規ライセンスを得ていないフィギュアは、税関で差し止められることもあります。さらに「侵害品と知りながら」購入・利用すれば、損害賠償の対象となる場合もあります。
肖像権の問題
実在人物を模したフィギュアを購入し、それを公開利用すると肖像権やパブリシティ権の侵害にあたるケースがあります。
👉 結論(購入者側)
所持するだけなら大きな問題にはなりにくいですが、公開・商用利用すると違法性が生じる可能性があります。安全に楽しむなら、公式ライセンス品か、完全オリジナル作品を選ぶのがベストです。
まとめ
- 作成者側:無断で著作物をAIで立体化すると、著作権・肖像権の侵害や利用規約違反になる可能性が極めて高い。必ず権利者から許可を得ること。
- 購入者側:所有するだけならリスクは小さいが、公開・商用利用で違法性が生じる恐れがある