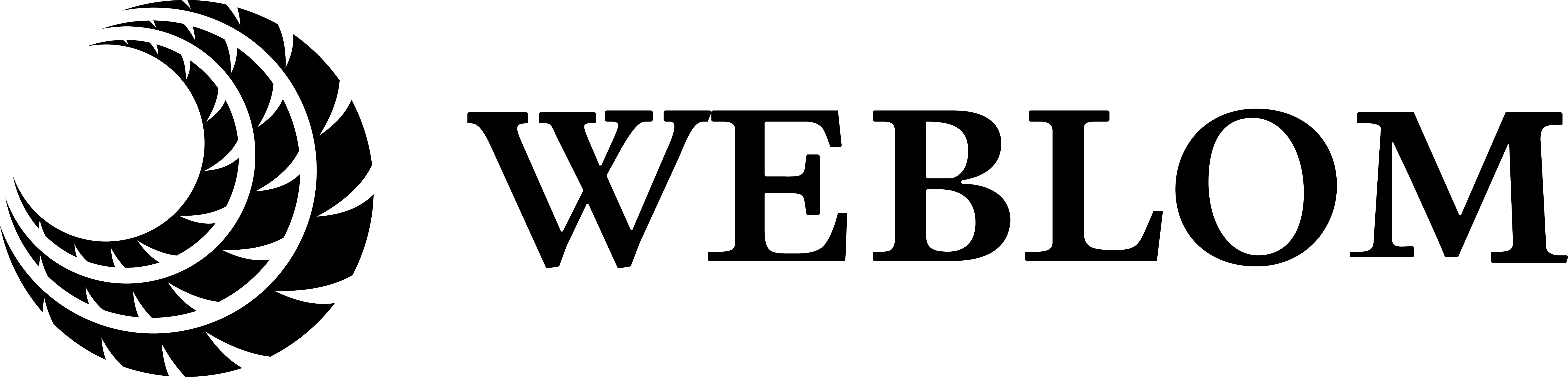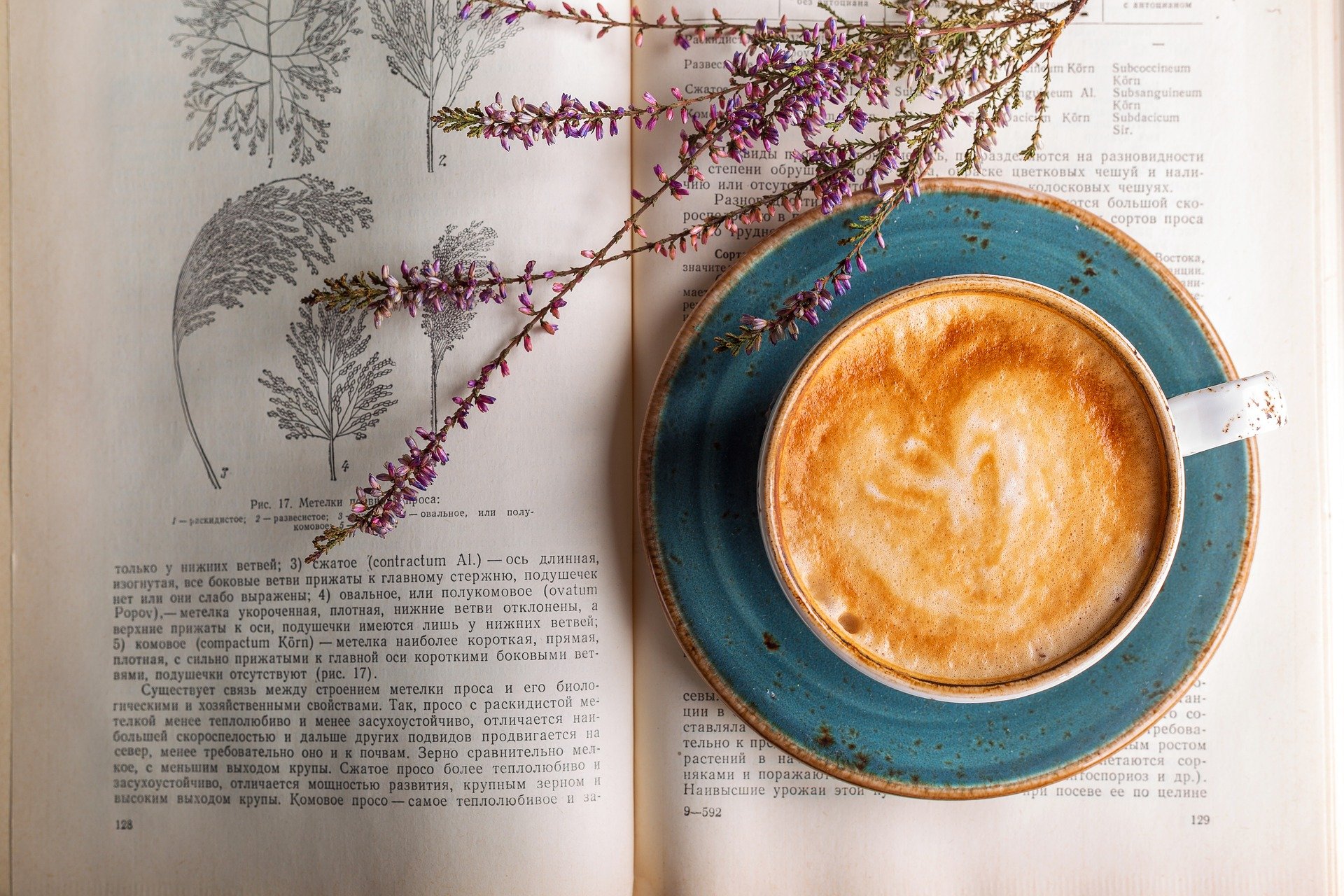政府・与党が本格的に検討している「走行距離課税」。自民党政権が国民の生活のことや経済を本当に何も考えていないことがよく分かりますね。
さすが、失われた30年の当事者たちです。
電気自動車(EV)の普及や暫定税率の廃止でガソリン税収が減ることを背景に浮上していますが、国民にとって実際の負担はどう変わるのでしょうか。
本記事では、想定される影響を「層別」に整理してわかりやすく解説します。
走行距離課税とは?
車の「所有」ではなく「利用」に応じて税を課す仕組み。という建前。
実際は、「利用」にも税を課すだけで、「所有」に際し減税はなさそうです。お得意の上乗せ課税ですね。
走った距離に応じて負担するため、一見すると公平に見えますが、実際には国民生活に大きな影響を与える可能性があります。
どの層にどれくらい影響があるか
| 層 | 想定される影響 | 具体例 |
|---|---|---|
| 都市部・車を持たない人 | 一見すると直接負担なし。ただし物流コスト上昇により物価が上がり、生活費が増加。 | スーパーの食品価格やEC配送料が上昇 |
| 都市部・車を所有する人 | 車利用が少なければ負担は軽め。ただしガソリン税など既存税制との二重課税になると増税感は強い。 | 週末ドライブ中心の家庭 |
| 地方の一般家庭(通勤・買い物で日常的に車使用) | 日々の移動距離が長く、負担増が顕著。生活必需品の値上げとも重なり、二重の打撃。 | 郊外在住の共働き世帯 |
| 物流業・運送業 | 最も直接的に打撃。走行距離が多いため税負担が大幅増 → 運賃値上げ不可避。 | 長距離トラック運転手、宅配業者 |
| 低所得層全般 | 車を所有していてもしていなくても、物価上昇で影響。特に車必須の地方の低所得世帯には痛手。 | 地方の高齢者世帯、非正規雇用世帯 |
走行距離課税がもたらす3つの懸念
- 実質的な国民負担の増加
車を使う人はもちろん、使わない人も「物価高」を通じて間接的に負担を背負うことになります。 - 地方と都市の格差拡大
公共交通が整っている都市部より、車依存の地方が圧倒的に不利。 - 二重課税のリスク
ガソリン税や重量税が残ったまま走行距離課税が導入されれば「増税」と受け止められる可能性が高いです。
まとめ
走行距離課税は「公平な制度」に見えますが、実際には 物流コストを通じて国民全体に広く負担を押し付ける可能性が高い 制度です。
特に地方や物流業界にとっては深刻な負担増となり、最終的には全国民が「物価高」という形で影響を受けるでしょう。
まさに、霞ヶ関で冷たいクーラーの風を浴びながら自分の懐だけを考えたような悪意丸出しの税制度です。
導入の是非は「税収確保」と「国民生活への影響」を天秤にかける議論になると考えられます。