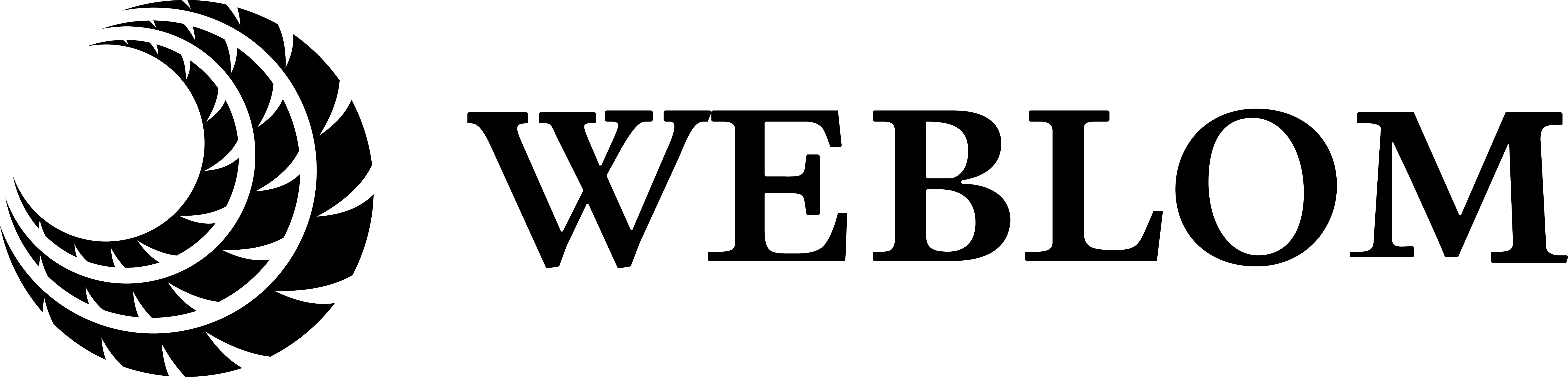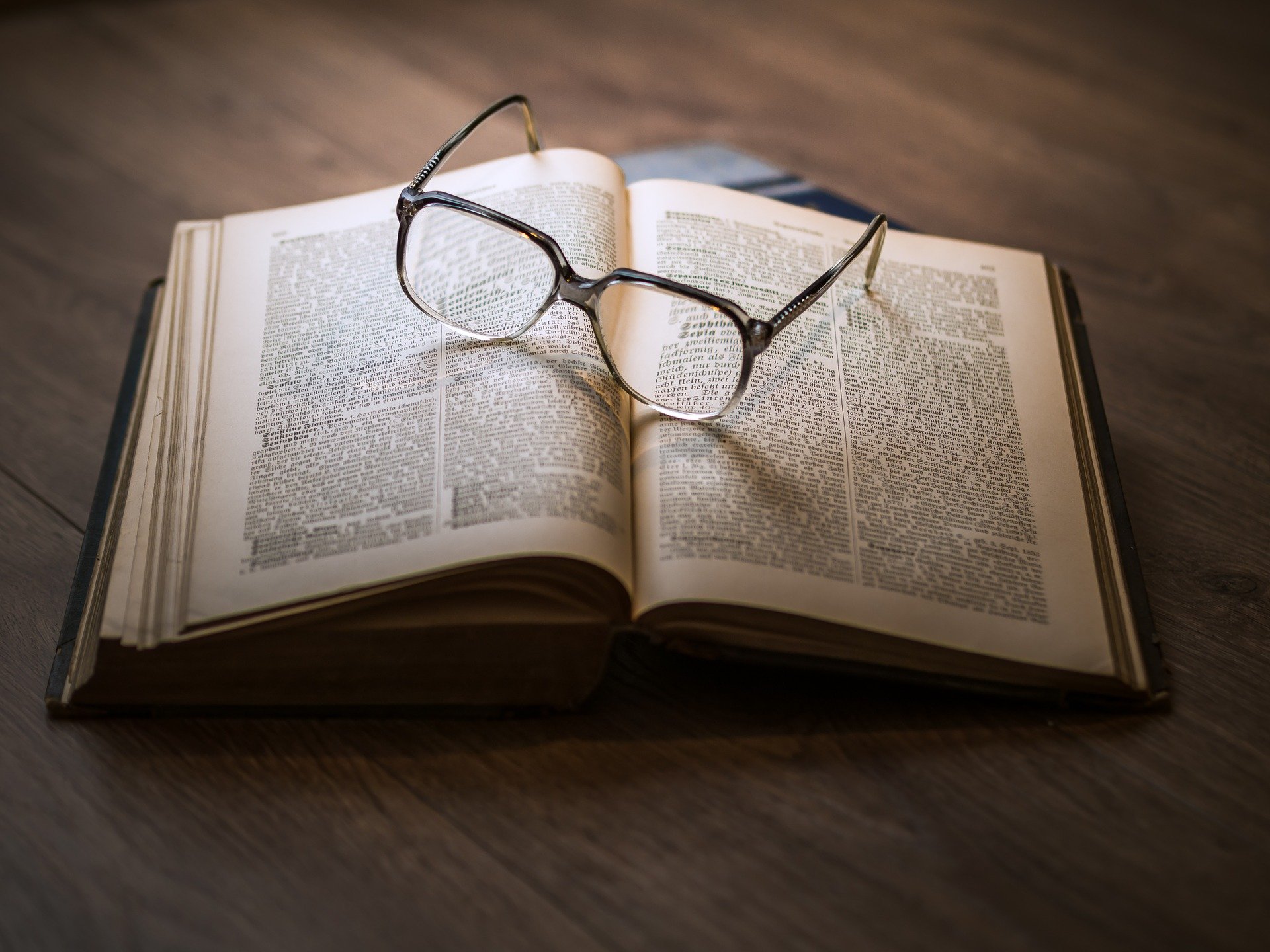沖縄県庁が、退職金の未払い があったにもかかわらず、時効を理由に支払わない方針を示した ことが問題となっています。
特に2014年度から2017年度に退職した 実習助手4人 については、「支払うべき退職金があるのに、法的時効を盾に支給を拒否している」状況です。
しかし、法律上の時効が成立していたとしても、本当に支払わなくてよいのか? また、県庁が 意図的に時効を待っていた場合、違法性を問うことはできるのか? この記事では、沖縄県庁の対応を検証し、法的観点から考察します。
何が起こったのか? 実習助手4人の退職金未払い問題
2025年2月、沖縄県教育委員会(県教委)は、2018年度~2022年度に退職した13人の退職金が過小支給されていた ことを明らかにし、総額1692万6千円 の追加支給を決定しました。
しかし、さらに調査を進めたところ、2014年度~2017年度に退職した実習助手4人 についても 同様に退職金が過小支給されていた ことが発覚しました。
問題点は、この4人に対して「支払うべきお金がある」と分かりながらも、沖縄県庁は時効を理由に支払わない方針を示したことです。
沖縄県庁の主張は次の通りです。
- 労働基準法では賃金(退職金含む)の 請求権は5年で時効(労基法115条)
- 地方自治法にも給与支払いの 時効(5年)がある
- そのため、2014~2017年度退職者には支払う義務がない
しかし、この対応にはいくつかの問題点があります。
本当に違法性はないのか? 時効を理由に支払わない問題点
沖縄県庁の主張通り、法律上の時効は5年で成立します。ですが、ここで重要なポイントは 「時効を利用して意図的に支払いを逃れたのではないか?」 という点です。
時効の悪用は「信義則違反」にあたる可能性
民法第1条第2項では、「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」 と規定されています。
つまり、
- 沖縄県庁が 未払いの事実を知りながら、意図的に黙っていた
- 時効を待つことを目的に支払いを避けた
といった事実があれば、信義則違反 で時効の主張が認められない可能性があります。
不法行為なら時効は最長20年まで遡れる
通常、退職金の請求権は5年で消滅しますが、県庁が故意に支払わなかった場合、不法行為として損害賠償請求が可能 です(民法709条)。
不法行為として認められれば、
- 時効は3年(2020年の改正後は5年)、または最長20年 まで遡ることができます。
つまり、もし「意図的に支払わなかった」と証明できれば、2014年退職者であっても 2034年まで請求可能 となる可能性があります。
過去の類似事例では「時効でも支払う」自治体もある
他の自治体では、同様の未払いが発覚した際に 「法的時効が成立していても、道義的責任から支払う」 という対応を取るケースもあります。
例えば、
- 東京都のある自治体では、過去の未払いを 「特例」として支給 したケースがある
- 民間企業でも、労使交渉の結果、時効後でも支払いを行った例 がある
沖縄県庁も、「時効だから払わない」という態度ではなく、道義的に支払う選択肢もあるはず です。
実習助手4人ができる対策は?
実習助手4人が支払いを求めるために、以下の手段が考えられます。
沖縄県庁への交渉・陳情を行う
- 県議会や労働組合を通じて「時効でも支払うべき」と訴える
- メディアに取り上げてもらい、社会的な圧力をかける
情報公開請求を行い、故意の隠蔽を証明する
- 県庁内で 「未払いがあると認識していた」証拠(内部文書、メールなど)を探す
- 証拠が見つかれば、信義則違反や不法行為として訴える材料 になる
法的手段(損害賠償請求)を検討する
- 弁護士に相談し、「不法行為による損害賠償」 を請求できるか判断する
- 訴訟を起こすことで、県庁が対応を見直す可能性がある
まとめ:沖縄県庁は本当に「支払わなくていい」のか?
沖縄県庁は、「時効だから支払わない」 という立場を取っています。
確かに、法律上は時効が成立していますが、
- 未払いを故意に隠していた場合、違法となる可能性 がある
- 道義的な責任を果たすべきではないか? という議論の余地がある
- 不法行為が認められれば、最長20年まで請求可能
という点を考えると、「時効だから終わり」では済まされない問題です。
もし実習助手4人が声を上げ、県庁や社会に訴えかけることができれば、支給される可能性はゼロではありません。
この問題は、沖縄県庁だけでなく、全国の公務員退職者にも関わる重要な問題 です。
今後の動向に注目しましょう。