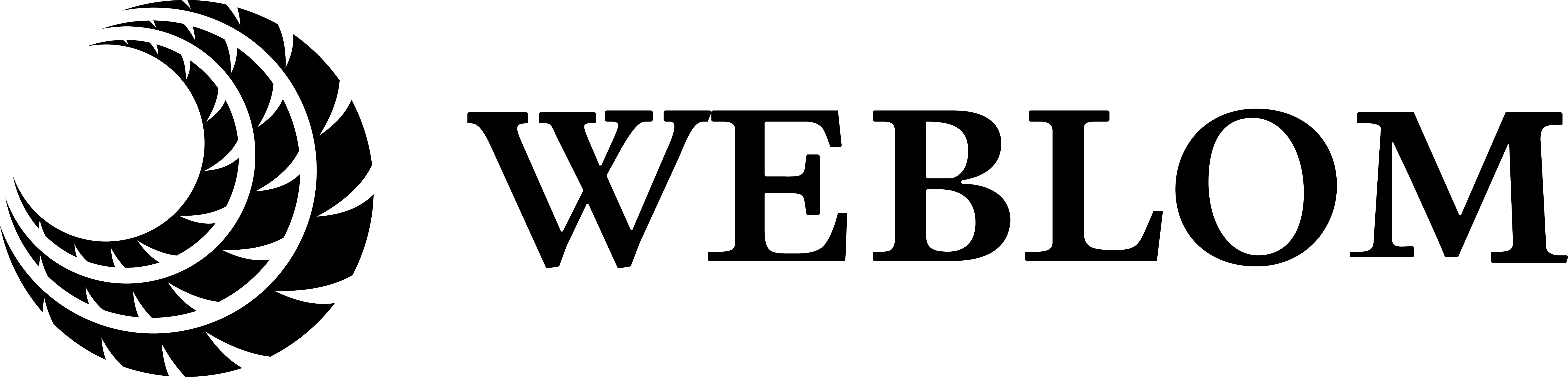はじめに
メタプラネット(証券コード 3350)の株価が暴落しています。
9月の海外公募増資を境に株価は900円から一時550円台まで急落。
その後も反発らしい反発は見られず、10月中旬には mNAV(理論純資産倍率)が 1.0 を割り込みました。
この急落は単なるビットコイン相場の下落ではありません。
むしろビットコイン価格は公募開始時からほぼ横ばいで推移しています。
それでも株価が半値まで崩れた背景には、増資スキームそのものの構造的な問題があると見られています。
メタプラネットの基本戦略とmNAVという指標
メタプラネットは「日本版マイクロストラテジー」を掲げ、ビットコイン(BTC)を主要資産として保有・拡大する戦略を取っています。
2025年9月には約5,400BTC(約936億円相当)を追加取得。保有枚数は合計25,000BTCを超えました。
このような企業を評価する際に用いられる指標が mNAV(Market Net Asset Value) です。
- mNAV > 1:保有BTC価値を上回る株価(プレミアム評価)
- mNAV < 1:保有資産価値を下回る株価(割安評価)
現在、mNAVが1を割り込んでおり、投資家心理に冷え込みが見られます。
この「mNAV割れ」は、ビットコインの価値よりも株価が安く評価されているという、信頼喪失のサインとも言えます。
なぜ株価が急落したのか
今回の暴落をめぐっては、「公募増資の仕組みを利用した空売りと現渡しのスキーム」が原因だという指摘が浮上しています。
公募価格の決定構造
9月に実施された海外公募増資では、
9月9日〜11日の終値の平均から最大10%ディスカウントという条件で価格が決められました。
つまり、基準期間中に株価が低いほど、海外投資家は安く株を取得できます。
これを狙って海外ヘッジファンドが空売りを仕掛け、株価を意図的に下げた可能性があると見られています。
結果、株価は10営業日ほどで900円→614円まで急落。
そして、その614円を基準に10%割引された553円が公募価格として決定されました。
現渡し疑惑:株価が戻らない理由
通常、空売りをすれば、いずれ買い戻す必要があり、その「買い戻し」が株価の下支えになります。
ところが今回は、空売りした投資家が公募で取得した株をそのまま現渡し(市場外での受け渡し)に使った疑いがあります。
この「現渡し」によって、買い戻しによる上昇圧力が市場から消えたのです。
結果として、株価は下がったまま反発せず、信用売り残高だけが異様に減る現象が確認されています。
サイモンCEO自身も「公募増資による空売りの現渡しは違法だ」とX上で投稿していますが、
実際には対応が取られず、泣き寝入りの形になっています。
株主の犠牲と会社の利益構造
このスキームによって誰が得をしたのかを考えると、皮肉な構図が浮かび上がります。
- 株主:短期間で株価が約4割減。保有比率も希薄化。
- 会社:株価下落でも大量の新株発行に成功。
- 受け入れ先:割安で大量の株式を取得し、現渡しでリスク回避。
つまり、株主が犠牲になり、会社と投資家が得をする仕組みだったという批判が出ています。
しかもメタプラネットは、調達した資金で31000BTC近い資産を「実質無料で手に入れた」構図になっています。
法的観点:訴訟は可能か?
現時点で明確な違法行為が確認されているわけではありません。
ただし、次のような法的論点は存在します。
- 市場操作(金融商品取引法第159条):意図的な相場誘導があった場合は違法。
- 忠実義務違反:取締役が株主利益を軽視した場合、株主代表訴訟の対象になり得る。
- 開示義務違反:IR情報やスケジュールを不十分に開示した場合、虚偽表示として問題視されることも。
証拠がそろえば、株主側から民事訴訟を起こす余地もあるでしょう。
ただし、実際に法廷で勝訴するには、「具体的損害」と「因果関係」の立証が必要です。
今後の注目ポイント
今後のメタプラネット株を左右する要因は次の5つです。
- 1株あたりBTC保有量の推移
希薄化が続く中、BTCの増加ペースが追いつくかが焦点。 - BTC相場の動向
BTCが下がればmNAVはさらに悪化。上昇すれば一時的な株価回復も。 - IRと説明責任
投資家への情報開示をどれだけ丁寧に行えるか。 - 規制当局の動き
市場操作疑惑が調査対象になる可能性。 - 資金調達の次の一手
優先株や新ワラントの発行など、追加希薄化のリスクも残る。
まとめ
今回のメタプラネット株価暴落は、単なる仮想通貨相場の変動ではなく、「資本政策の設計ミス」や「市場操作的スキーム」によって引き起こされた可能性があります。
サイモンCEOは「10000BTCの購入で株価が上がる」と考えていた節がありますが、
結果的には逆に**“株主離れと信頼喪失”**を招く結果になりました。
ビットコインを保有する企業としてのポテンシャルは依然ありますが、株主への配慮と説明責任を欠いた経営を続ける限り、市場は再び同社に信頼を寄せることは難しいでしょう。
この事件は、仮想通貨連動企業が抱える「成長と希薄化のジレンマ」を浮き彫りにしました。
株主を守る仕組みが整わない限り、同様の構図は再び繰り返されるかもしれません。