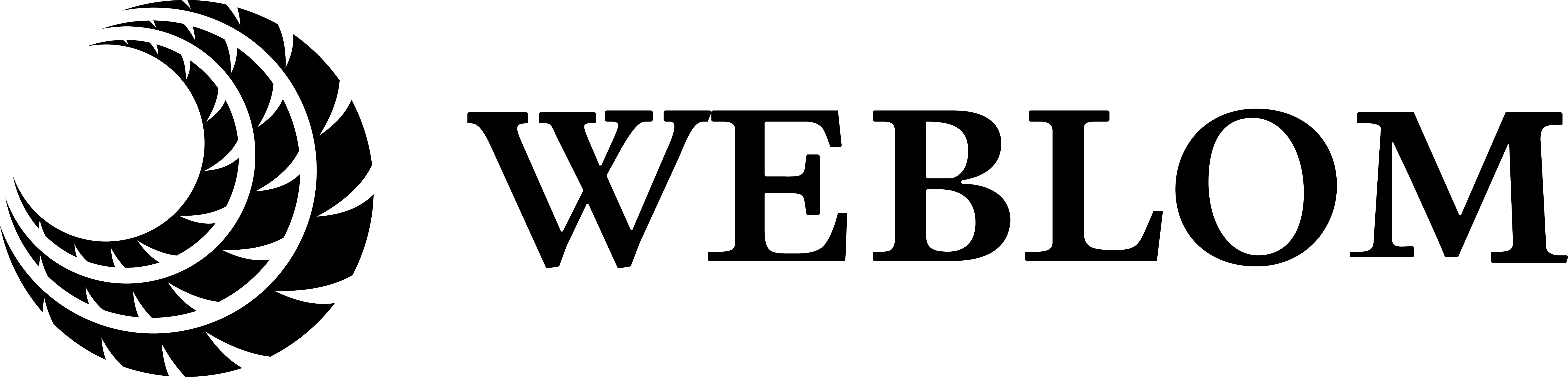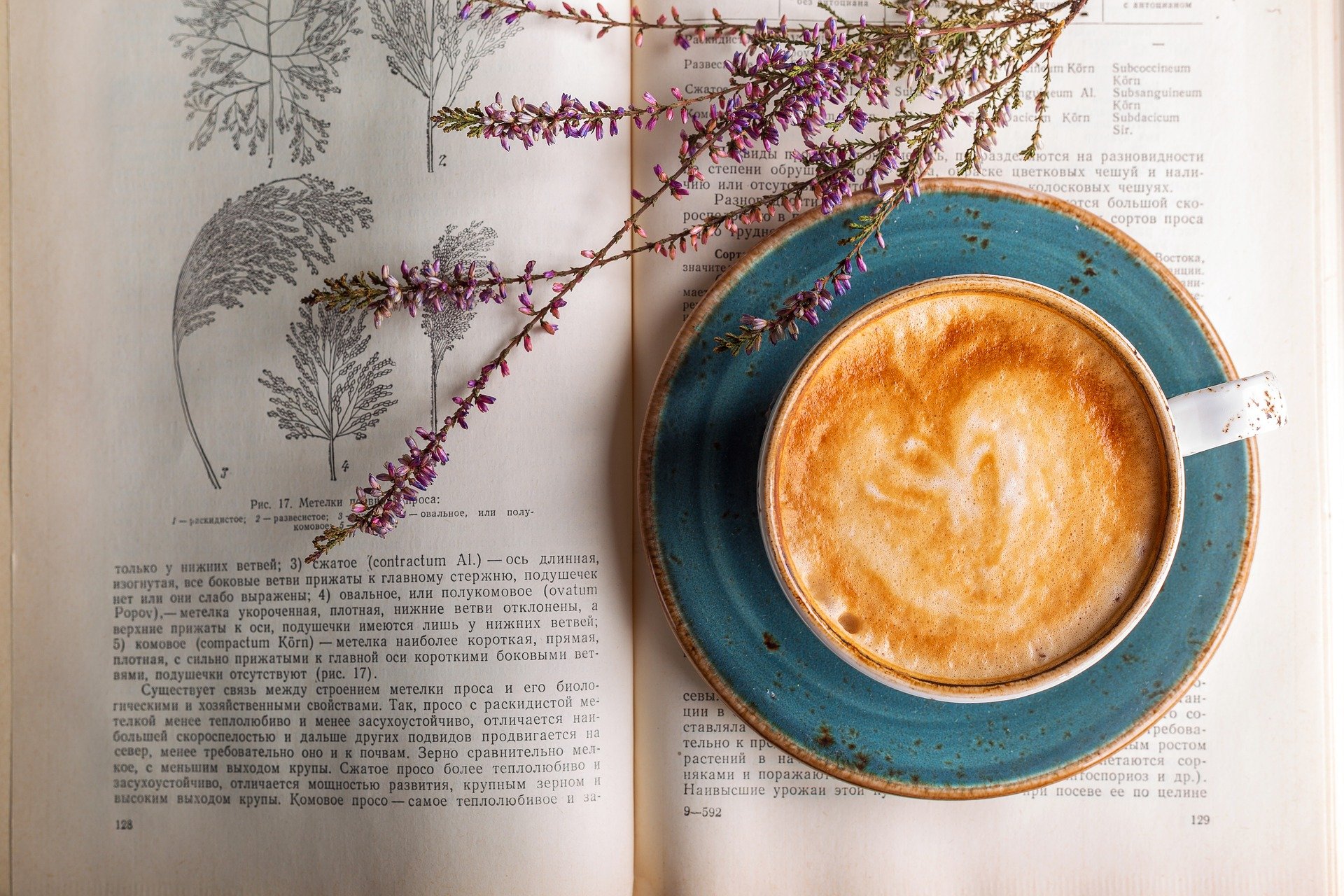近年、インターネット上での誹謗中傷や権利侵害が社会問題となっています。
これに対応するために、日本政府は「情報流通プラットフォーム対処法」(通称:情プラ法)が2025年4月から施行されるようです。
しかし、この法律が「SNS規制」であり、「言論の自由を奪うものだ」と誤解されることが多く、X(旧Twitter)などで議論が盛んになっています。
この記事では、情プラ法の正しい内容を解説し、なぜ「言論の自由を奪うSNS規制」ではないのかを明確にしていきます。
※当記事は現政府を肯定し庇うようなものではありません。あくまで、情プラ法の事実をお伝えします。
「情プラ法」とは何か?
情プラ法は、従来の「プロバイダ責任制限法」を改正した法律で、2025年4月1日から施行されます。この法律の目的は、インターネット上の誹謗中傷や違法情報に迅速かつ適切に対応することであり、以下のような変更点があります。
主な変更点
- 投稿削除対応の迅速化:プラットフォーム事業者は、不適切な投稿に対して迅速な削除対応を求められる。
- 対応結果の通知義務:削除要請を受けた場合、事業者は7日以内に申請者へ通知する義務がある。
- 運用状況の透明化:削除対応の運用状況を公開し、透明性を確保することが義務付けられる。
この法律は、ユーザーの表現の自由を制限するものではなく、主にプラットフォーム側の対応を明確にするものです。
「言論の自由を奪うSNS規制」ではない理由
多くの人が「政府がSNSを規制し、自由な発言を抑え込むのではないか」と懸念していますが、それは誤解です。以下の理由から、情プラ法は言論の自由を制限するものではありません。
投稿の自由は維持される
この法律は、SNSや掲示板などのユーザーの投稿を制限するものではありません。むしろ、被害を受けた人が適切に対応できる仕組みを整備することが目的です。
対象となるのは誹謗中傷や違法情報のみ
削除の対象となるのは、
- 名誉毀損やプライバシー侵害にあたる投稿
- 違法行為を助長する投稿
- 虚偽の情報による営業妨害 など、法律に基づいた基準で判断されます。
一方で、
- 一般的な意見や批判
- 政府や企業への異論
- 正当なジャーナリズム活動 などは、削除の対象外です。
政府による検閲ではない
削除の判断を行うのは、あくまでプラットフォーム事業者であり、政府が直接投稿を監視・削除するわけではありません。事業者が法的基準に沿って対応する仕組みになっています。
ネット上で広がる誤解とその正しい解釈
X(旧Twitter)では「政府が都合の悪い発言を消すための法律だ」といった意見が見られます。しかし、これは事実ではありません。
【誤解1】「政府が検閲して自由な発言を削除する」
→ 実際は、削除判断はプラットフォーム事業者が行い、政府が直接投稿を監視するわけではない。
【誤解2】「批判的な意見がすべて削除される」
→ 実際は、削除対象は違法情報や誹謗中傷のみで、正当な意見表明は制限されない。
削除対象となる具体例
- 他人の氏名・住所・電話番号を無断公開し、プライバシーを侵害する投稿
- 特定の個人や団体を侮辱・誹謗中傷する投稿
- 詐欺や犯罪を助長する情報(違法薬物の売買、犯罪の指南など)
- デマや虚偽情報を流布し、他者の名誉や企業の営業を著しく損なう投稿
【誤解3】「削除基準が不明確で恣意的に運用される」
→ 実際は、法律には削除基準が明確に定められており、対応の透明性も確保される。
※国が拡大解釈する可能性は否めない。
今後の影響と私たちができること
SNSを利用する上での注意点
- 投稿内容を見直す:他人を誹謗中傷するような投稿は控える。
- 削除要請の仕組みを理解する:万が一被害を受けた場合に、適切に対応できるようにしておく。
- 情報の発信者として責任を持つ:事実に基づいた発言を心がける。
不当な削除に対する異議申し立て方法
もし、自分の投稿が不当な理由で削除されたと感じた場合、プラットフォームごとに異議申し立ての手続きがあります。各サービスのガイドラインを確認し、必要に応じて対応しましょう。
まとめ
情プラ法は、インターネット上の誹謗中傷や違法情報に適切に対応するための法律であり、言論の自由を奪うSNS規制ではありません。
しかし、誤解が広がることで、不要な不安を抱く人も多いのが現状です。正しい情報を広めることで、より健全なインターネット環境を作ることができます。