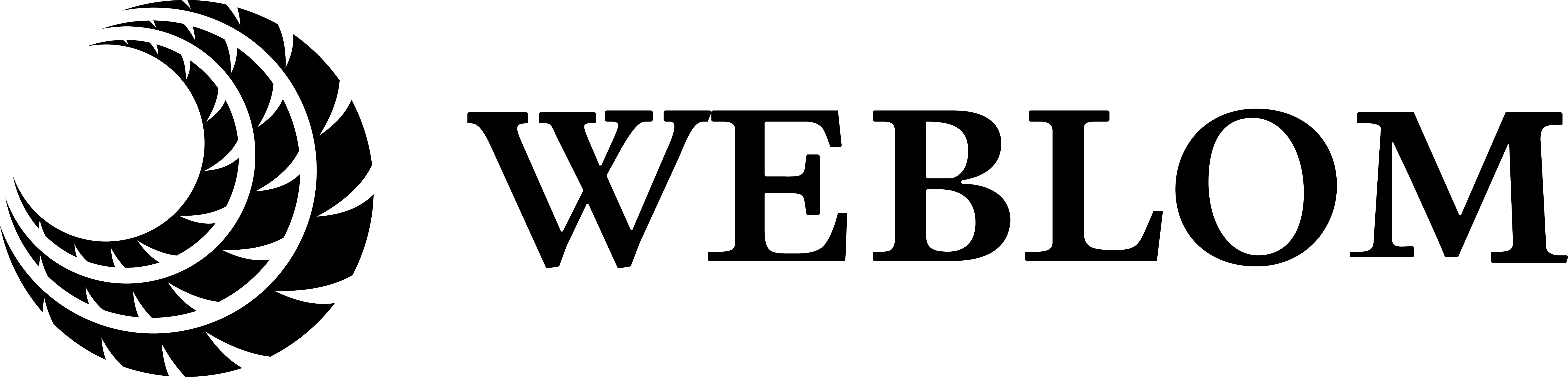近年、SNS上でAIを使ったフェイク画像が拡散され、それに伴う虚偽情報が問題になっています。山火事に対して、兵器での攻撃などといった悪質なものが増えてきました。AIを使い、画像まで作成されているので、より一層注意が必要です。
特に、山火事のような災害に関するデマは人々を混乱させ、実際の対応に支障をきたす可能性があります。
では、フェイクニュースはそもそも違法なのか?
本記事では、AIを使ったフェイク画像の拡散が日本の法律において違法となるケースについて解説します。
フェイク情報を拡散することの違法性
AIで生成したフェイク画像を使用して虚偽の情報をSNSなどで拡散する行為は、法律に違反する可能性が高いです。
以下の法律が適用される可能性があります。
偽計業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の情報を流して自治体や消防、警察などの業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
例:
- 「◯◯市で大規模な山火事が発生している」というデマを拡散し、消防が不要な出動をするよう誘導した場合
最近のは、山火事の原因に対するフェイク情報なので、これに該当するかは微妙なところです。
威力業務妨害罪(刑法234条)
フェイク画像を使って恐怖や混乱を引き起こし、公共機関や企業の業務を妨害した場合も処罰の対象となります。
軽犯罪法(第1条 第33号)
虚偽情報を流布し、社会に混乱を招いた場合、拘留または科料(1万円未満の罰金)が科される可能性があります。
今回の山火事フェイクニュースだと、これが一番近いかもしれません。
名誉毀損罪・信用毀損罪(刑法230条、233条)
特定の企業や個人を対象に、「〇〇が山火事を放火した」といった虚偽情報を拡散した場合、名誉毀損罪や信用毀損罪が適用される可能性があります。
偽計詐欺罪(刑法246条)
フェイク画像を使って寄付や支援を募り、金銭を騙し取った場合、詐欺罪に問われる可能性があります。
実際の事例とリスク
実際、日本でも災害時のデマ投稿による逮捕事例が報告されており、海外でもディープフェイクを使った偽情報の拡散が問題視されています。
特に、災害に関連するデマは迅速な対応を妨げるため、厳しく取り締まられる傾向があります。
能登半島地震でも悪質なフェイクニュースがあったのが記憶に新しいですね。
まとめ
AIによるフェイク画像を使ってデマを拡散する行為は、刑事罰の対象になる可能性が高く、社会的にも大きな問題となるため、絶対に避けるべきです。
災害時の情報は、公的機関や信頼できるメディアからの情報を確認し、誤った情報を拡散しないよう注意しましょう。
フェイク情報の拡散は、単なる「いたずら」では済まされないケースが増えています。SNSの情報を鵜呑みにせず、情報の発信・拡散には慎重になりましょう。